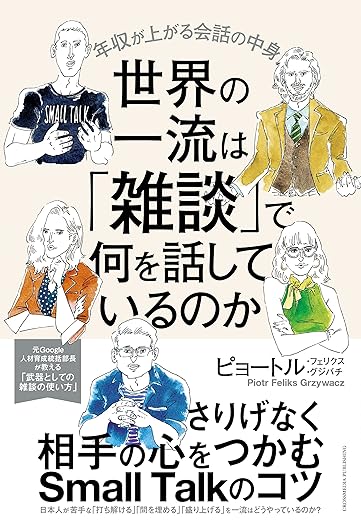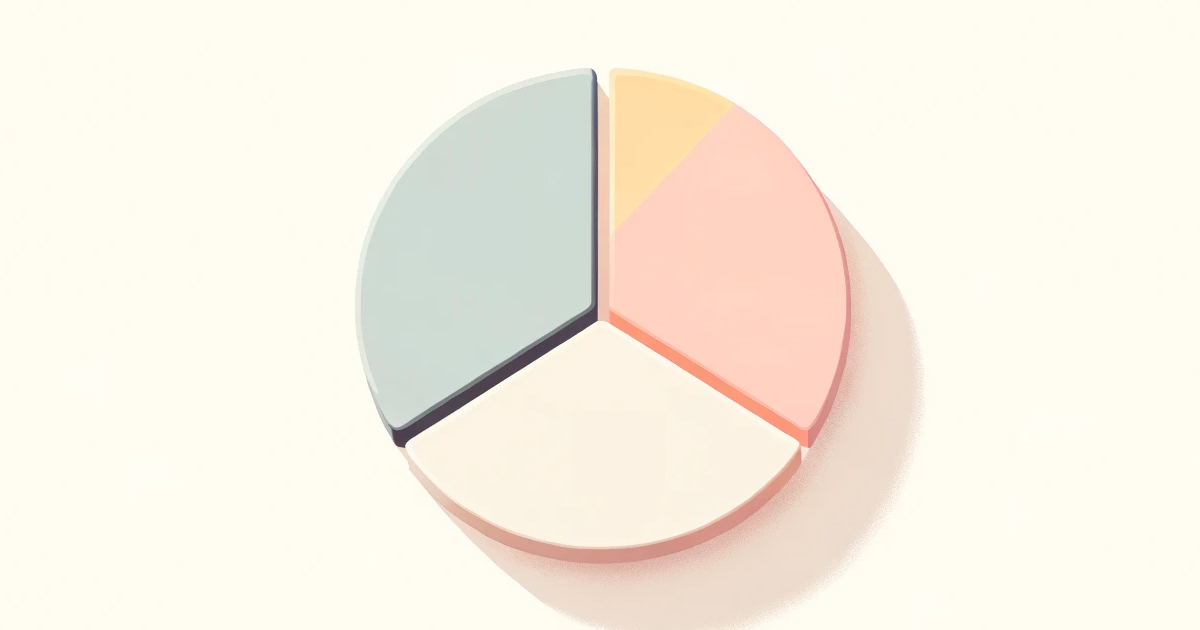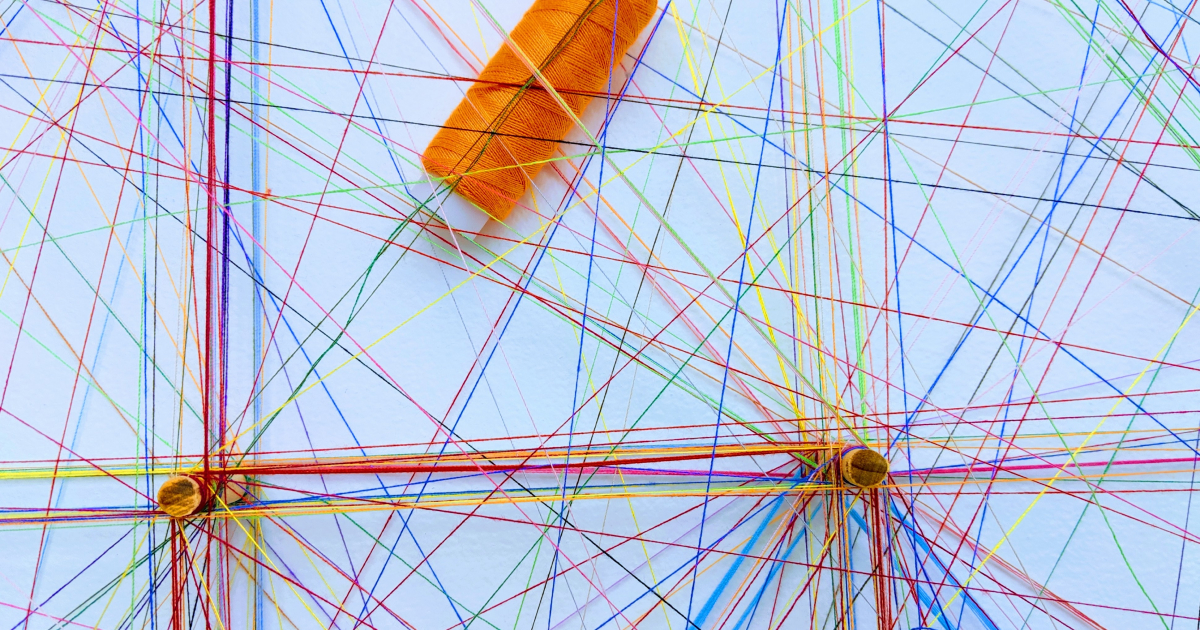雑談で何を話すべきか

「雑談は大切」とよく言われる。
自分も1on1を行う際には雑談を可能な限り入れるように心がけているが、逆に雑談しよう!と構えすぎてしまうと難しいなと思う。
そこでPrime Readingにて下記の本が読めるようになっていたので読んでみた。
雑談の意図
多くの日本人ビジネスマンは、「雑談が上手い人=おしゃべりが上手で、面白い話をする人」と考えているようですが、ビジネスの現場では、それだけでは不十分です。世界基準のビジネスの最前線では、「明確な意図を持ち、そこに向かって深みのある会話ができる人」こそが「雑談の上手い人」とされています。
普段の雑談に「意図」を持って挑んだことはほとんどない。なんとなく場をつなぐものだと考えていた。しかし、意図ある雑談こそが信頼や関係性を築く大切な一歩なのだ。
雑談が苦手な理由
雑談が苦手と感じている人の多くは、「目的のない会話」が不得意な人たちです。
目的がなければ「何を話せばいいのか」が分からなくなる。しかし少し視点を変えれば、雑談にはしっかりとした役割がある。
- 職場のつながりを生む
- 信頼感を高める
- 心理的安全性をつくる
- ミーティングで発言しやすくなる
- 仕事のモチベーションを高める
こうして見ると、雑談はチームを強くするための「仕組み」でもある。
自己開示の大切さ
多くの人は相手に質問して話を広げようとしがちだが、それだけでは質問攻めのような感じになってしまい、なかなか距離は縮まらない。
自分自身のことを積極的に話すことで「この人は自分に心を開いてくれている」という印象を与えることができ、安心感を持ってもらえる。これは意識したいポイントだ。
ラポールを築く
雑談の目的は「ラポール」を作ることだと書かれている。ラポールとは、お互いが心を開き、安心して話せる関係のこと。心理的安全性とほぼ同じ意味に感じたが、雑談がその基盤になるのは納得感がある。
面白かったのは、立場の弱い人にもしっかり関心を寄せるという話だ。
海外の優れたビジネスマンは、会議で「部長→新卒→課長→係長」といった意外な順番で発言の機会を与え、幅広い視点を引き出す。
こうしたファシリテーションも「雑談の延長線」にある。
雑談にも準備と復習がいる
雑談にも「予習」と「復習」が必要だ。前回話したことを覚えておく、同じ質問を繰り返さない。
こうした小さな配慮が信頼を深める。
自分も普段1on1の際に議事録メモは取っているが、週を重ねると埋もれてしまうので、大事な情報は別でメモに残すようにしている。
まとめ
雑談は「ただの会話」ではなく、
- 信頼をつくる
- 心理的安全性を育てる
- チームのパフォーマンスを高める
ための強力な武器である。
面白い話をする必要はない。大事なのは、相手を知ろうとする意図を持ち、自分自身のことも開示し、安心できる関係をつくること。
そう考えると、雑談がぐっと意味のあるものに感じられる。